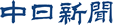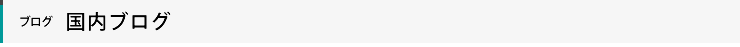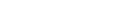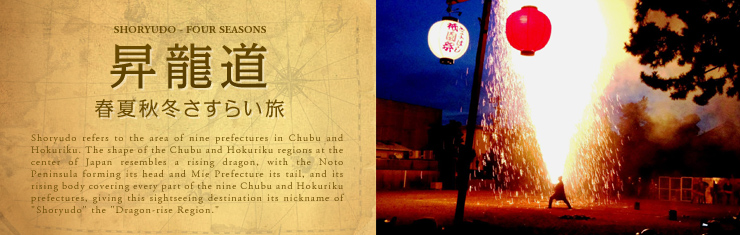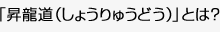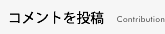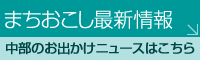桜咲く水の都・大垣をぶらり歩く
2014年4月 7日
岐阜県大垣市は水の都。
豊富な地下水から自噴する井戸が各所にあるほか、
市内中心部を流れるかつて大垣城の外堀であった水門川沿いに家並みが並ぶことからも
水の都としてのイメージが浸透している。


JR大垣駅の南口を出て東方向に少し歩くと、市内中心部の趣ある水門川沿いの遊歩道が現われる。
散策は何も迷うことはない。川沿いにのんびり歩いていくだけでいい。


桜の咲く時期には、「水の都おおがき舟下り」が開催されている。
歩くのもよし、舟に乗ってのんびり桜を観賞するもよし。
歩いていけば、途中、水の都と言われるゆえんでもある自噴する井戸や水の流れを何か所かで見ることもできる。
夏であれば、のどを潤してくれるオアシスになるだろう。



ほぼ散策路の終着点に近づくあたりに、少し開けた「四季の広場」がある。
柳の木が川面に映え、桜とのコントラストを美しく演出する。
川べりには降りて行くこともでき、そこから見上げる桜も美しい。



散策路の終着点には、松尾芭蕉が奥の細道の旅を終えた「奥の細道むすびの地」がある。
ここで約2kmの水門川沿いの散策は終わる。
芭蕉が江戸から東北、北陸、東海と150日にわたって歩いてきた最後のむすびの地がここ。
そんな旅人浪漫も感じられるのも魅力である。
そこには、奥の細道むすびの地記念館もあり、芭蕉が歩んだ歴史を知ることができる。


今も残される住吉灯台は当時の川湊の姿を思い起こさせてくれる。

 ここからは、同じ川沿いを歩いて戻るもよし、
ここからは、同じ川沿いを歩いて戻るもよし、関ヶ原の戦いの時に西軍の石田三成の本拠地ともなった由緒ある大垣城を見学するなり、
かつての美濃路を辿りながら帰るなり、趣に応じて散策すればよい。

駅から気軽に歩いていける旅情あふれる水の都・大垣めぐり。
特に、この桜の咲く時期は最上級に素晴らしい。

- 田中 三文 (たなか みつふみ)
愛知県豊橋市生まれ。
出版社勤務を経て、現在は三菱UFJリサーチ&コンサルティング 政策研究事業本部 上席主任研究員。
愛知大学地域政策学部非常勤講師(観光まちづくり論)
地域を盛り上げる観光事業や集客計画など、手がけてきたプロジェクトは数知れず。
2012年より2014年まで昇龍道プロジェクト推進協議会・台湾香港部会長を務め、
同エリアのインバウンド促進計画や外国人受入環境整備などにも力を注いでいる。
旅と写真とロックを愛する仕事人で、公私ともに、さすらいの旅人として各地を巡っている。

日本の真ん中に位置する中部北陸地域の形は、能登半島が龍の頭の形に、三重県が龍の尾に似ており、龍の体が隈無く中部北陸9県を昇っていく様子を思い起こされることから同地域の観光エリアを「昇龍道」と呼んでいます。
この地域には日本の魅力が凝縮されており、中部北陸9県が官民一体となって海外からの観光客誘致を促進する「昇龍道プロジェクト」も好調です。このブログでは、「昇龍道」の四季折々の姿を写真と文章で紹介していきます。
投稿についての注意事項
- このブログへのご質問については、内容によってお答えできない場合や、回答に時間がかかる場合があることをご了承ください。